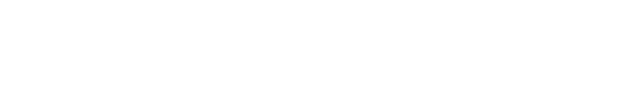気管支喘息について
気管支喘息について
〜正しく知って、しっかり治す〜
1. はじめに
気管支喘息(ぜんそく)は、気道(空気の通り道)に慢性的な炎症が起こり、発作的にせきや息苦しさ、ゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音が出る病気です。
日本では子どもから大人まで幅広い年代にみられます。特に成人期に発症する喘息は長く付き合う必要があり、適切な治療と生活習慣の工夫が大切です。
喘息は放置すると発作が悪化し、命に関わることもありますが、正しい治療を続ければ発作をほとんど起こさず、普通の生活を送ることが可能です。
2. 気管支喘息の仕組み
(1) 気道の炎症
喘息では、気道の内側に慢性的な炎症が起こります。
この炎症によって、気道は腫れやすくなり、ちょっとした刺激(花粉、ほこり、冷たい空気など)でも過敏に反応します。
(2) 気道の収縮
炎症があると、刺激を受けたときに気道の筋肉がぎゅっと収縮します。そのため空気の通り道が狭くなり、呼吸が苦しくなります。
(3) 痰(たん)の増加
炎症により気道の粘液が増え、痰が絡んで息がさらにしづらくなります。
3. 主な症状
-
ゼーゼー、ヒューヒューといった笛のような呼吸音(喘鳴)
-
息苦しさ
-
夜間や明け方に強くなるせき
-
運動後の息切れやせき
-
季節の変わり目、風邪の後にせきが長引く
※特に夜間や早朝に症状が強くなるのは、気道の反応がこの時間帯に高まるためです。
4. 喘息の原因と悪化因子
喘息は一つの原因だけで起こるわけではなく、複数の要因が関わります。
アレルギー性
-
ハウスダスト(ほこり、ダニ)
-
ペットの毛やフケ
-
花粉
-
カビ
非アレルギー性
-
運動(特に冬場)
-
冷たい空気
-
タバコの煙
-
大気汚染
-
強いにおい(香水、消臭剤など)
-
ストレスや過労
5. 喘息の診断
(1) 問診
症状の出る時間帯、季節、環境との関係、家族歴などを詳しく聞きます。
(2) 呼吸機能検査
スパイロメーターで肺活量や空気の流れを調べます。発作がないときでも異常がわかる場合があります。
(3) 気道過敏性試験
特殊な薬や冷気を吸入して気道の反応性を調べます。
(4) アレルギー検査
血液検査でアレルゲン(原因物質)を特定します。
6. 喘息の治療方針
喘息治療の目的は「発作を予防し、日常生活に支障がない状態を保つこと」です。
現在の治療は「症状が出たら薬を使う」だけでなく、「症状を出さないようにする」予防的治療が中心です。
7. 治療の種類
(1) 長期管理薬(予防薬)
毎日使うことで炎症を抑え、発作を起こりにくくします。
-
吸入ステロイド薬(ICS):最も重要な治療薬
-
長時間作用型β2刺激薬(LABA):ICSと併用
-
ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA):内服タイプ
-
テオフィリン徐放薬:気管支を広げる
(2) 発作治療薬(症状が出た時に使用)
-
短時間作用型β2刺激薬(SABA):速効性の吸入薬
-
抗コリン薬(短時間型)
8. 吸入薬の使い方の重要性
吸入薬は薬を直接気道に届けられるため効果が高いですが、正しい使い方をしないと十分な効果が得られません。
医師や薬剤師から指導を受け、定期的に吸入手技を確認することが大切です。
9. 発作時の対応
-
軽い発作:発作治療薬を吸入
-
中等度以上:吸入後も改善がなければすぐに受診
-
重症発作:会話が困難、顔色が悪い、唇が紫色 → 迷わず救急要請
10. 生活上の注意点
-
アレルゲン回避(掃除、空気清浄機、寝具の管理)
-
タバコ・受動喫煙を避ける
-
風邪予防(手洗い、マスク、ワクチン)
-
運動は主治医と相談しながら安全に
-
睡眠と栄養をしっかり取る
-
ストレス管理
11. 喘息と運動
喘息でも運動は可能です。むしろ適度な運動は肺機能の維持やストレス解消に役立ちます。
ただし、発作が出やすいときや季節は無理をせず、ウォーミングアップ・クールダウンを十分に行いましょう。
12. 喘息の予後と長期管理
喘息は長く付き合う病気ですが、治療と管理で発作をほぼゼロにすることも可能です。
大切なのは「症状がなくても治療を続けること」です。
炎症は症状がなくても残っているため、薬をやめると再発する可能性があります。
13. まとめ
-
喘息は気道の慢性炎症による病気
-
治療の中心は吸入ステロイド薬による炎症コントロール
-
発作を予防するためには毎日の管理が重要
-
適切な生活習慣と薬の継続で普通の生活が可能
当院では、患者さん一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせた治療計画を立て、定期的な検査と指導を行っています。
気になる症状がある方は、早めにご相談ください。