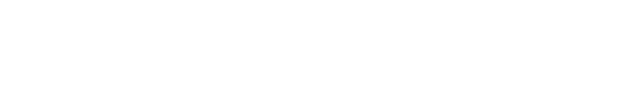電解質異常とは
血液の水電解質濃度は極めて狭い範囲にコントロールされています。このために細胞1個1個の効率的な働きが保たれているのです。例えば血清カリウムは3.5~5.0 mEq/Lの狭い範囲に調節されていて、高すぎれば不整脈をきたし、低すぎれば脱力や腸閉塞を招き命にかかわります。この精緻な調節の主座は腎にあります。電解質濃度の異常を検知するセンサーは腎あるいは腎以外にありますが、その異常はホルモンや神経を通じて伝達され、最終的に腎における排泄量が決定されます。
私たちの祖先はミネラルを豊富に含む海水から誕生し、陸に上がるようになって進化した腎に,水電解質を不必要に排泄しないような機構を授けたと考えられます。
ところで水電解質の恒常性が破綻して生じた状態が水電解質異常であり,このような内部環境の破壊は生命の危険を招きます。したがって水電解質異常を積極的に発見し,適切に治療することは臨床的に極めて大切なことです。最初の発見はもっぱら血液検査による異常値がきっかけになりますが、普段と異なる患者さんの症状や客観的なサインから見つかることも多いです(表1)。
水電解質異常値へのアプローチ
さて電解質の異常低値をみた場合,病態生理へのアプローチの基本は図 2 左のようになります。低 カリウム血症を例に説明します。低カリウム血症の原因として主な原因は 4 つ考えられます。カリウムの摂取不足,嘔吐・下痢など消化管からのカリウム喪失,細胞の外側から内側への移動,腎からのカリウム喪失の4つです。前の2つは病歴,病状から容易に判断できます。細胞内外のシフトに関わる要因は比較的限られているためこれもそれらの有無を検索すればよい(図 8)。最も診断が難しいのは腎からの喪失があるのかどうかという点であり,そのためには電解質の排泄率を求めるのがよい方法です。
一方,電解質の異常高値のアプローチの基本は図 2 右のようになります。ここでも高カリウム血症を例にとると,主たる原因として,摂取過剰,体内での産生,細胞の外側への移動,腎からの排泄低下の 4 つがあげられます。
このように,水電解質異常の病態生理の原則は,腎が原因か腎以外が原因かに絞られます。そのうちに具体的な例について記述したいと思います。
2023/09/22初稿
--------------------
すこし電解質そのものについての知識を深めましょう。
厚生労働省が勧める1日の野菜摂取量がどのくらいかご存じですか?
1日350 gにとされていますが、この量がどのくらいかイメージつきますか?
通常のサラダボウルの野菜の重さは100~120 gですので、その3倍の量になります。したがって、毎食サラダを食べないと追いつきません。
ところで、野菜350 gに含まれるカリウムの量は、どのくらいになると思いますか?
野菜に含まれるカリウム量は種類によって異なりますが、一般的な野菜の平均的なカリウム含有量から推定すると、350 gの野菜には約1000~1500mg(1.0~1.5 g)のカリウムが含まれていると考えられます。
参考(野菜100gあたりのカリウム含有量):
- ほうれん草(生):690 mg
- 小松菜(生):500 mg
- キャベツ(生):200 mg
- にんじん(生):300 mg
- トマト(生):210 mg
- きゅうり(生):200 mg
例:
- ほうれん草や小松菜などカリウムが多い野菜を多く摂ると、350 gで1,500 mg以上になる可能性があります。
- キャベツやきゅうりなどカリウムが少なめの野菜が多い場合は、1,000 mg前後にとどまります。
注意点:
- 調理(茹でる・煮る)によってカリウムが流出し、減少することがあります。
- 腎機能が低下している場合、カリウムの摂取量には注意が必要です。
一方で、果物に含まれるカリウム量についてはどうでしょうか。
果物には比較的多くのカリウムが含まれており、種類によって含有量は異なります。以下に主な果物のカリウム含有量(100 gあたり)を示します。
果物のカリウム含有量(100 gあたり)
- バナナ:360 mg
- キウイフルーツ:290 mg
- アボカド:720 mg
- メロン:340 mg
- いちご:170 mg
- ぶどう:130 mg
- みかん:150 mg
- りんご:120 mg
- スイカ:120 mg
- 柿:170 mg
果物350 gに含まれるカリウムの目安は以下のようになります。
- カリウムが多い果物(バナナ、アボカドなど)
→ 1,000~2,500 mg(1.0~2.5 g) - カリウムが少なめの果物(りんご、ぶどうなど)
→ 400~600 mg
ポイント
- バナナやアボカドは特にカリウムが豊富
→ 腎機能が低下している人は摂取量に注意。 - 水分が多い果物(スイカ、みかんなど)はカリウムが比較的少なめ
→ 水分補給とともに適度なカリウム補給ができる。 - 加工品(ジュースやドライフルーツ)ではカリウム濃度が変わる
→ ドライフルーツは水分が減るため、カリウムが濃縮されやすい。
2025/04/29 第2稿