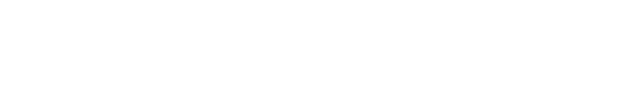糖尿病について
糖尿病とは?
糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高くなる疾患です。食事から摂取した糖分は、膵臓から分泌される「インスリン」というホルモンの働きによって細胞に取り込まれ、エネルギーとして利用されます。しかし、糖尿病になるとインスリンの分泌が不足したり、十分に働かなくなったりするため、血糖値が高い状態が続きます。
糖尿病は世界的に増加しており、生活習慣病の一つとして広く認識されています。特に2型糖尿病は、食生活の欧米化や運動不足の影響で増加傾向にあります。糖尿病は進行するとさまざまな合併症を引き起こすため、早期発見・早期治療が重要です。
糖尿病の種類
糖尿病には主に以下の4つのタイプがあります。
1. 1型糖尿病
自己免疫の異常により、膵臓のインスリンを分泌する細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなるタイプです。主に若年層に発症し、生涯にわたりインスリン治療が必要となります。発症の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因やウイルス感染などが関与していると考えられています。
2. 2型糖尿病
生活習慣や遺伝が関係する糖尿病で、日本人に最も多いタイプです。インスリンの分泌量が不足したり、効果が弱くなったりして血糖値が高くなります。食事や運動の改善、薬物療法が主な治療法です。初期症状が乏しいため、健康診断で指摘されて初めて気づくことが多いです。
3. 妊娠糖尿病
妊娠中にホルモンバランスの変化により血糖値が上昇することがあります。適切な管理をしないと、母体や胎児に影響を及ぼす可能性があるため、医師の指導のもとでの管理が重要です。出産後に血糖値が正常に戻る場合もありますが、将来的に2型糖尿病を発症しやすくなるため、定期的な健康管理が必要です。
4. その他の糖尿病
遺伝的な要因や病気、薬剤の影響などにより発症するタイプの糖尿病もあります。例えば、遺伝性のMODY(Maturity Onset Diabetes of the Young)や、膵臓の病気に伴う糖尿病などが挙げられます。
糖尿病の症状
糖尿病は初期段階では自覚症状が少なく、気づかないうちに進行することが多いです。しかし、以下のような症状が現れることがあります。
-
のどの渇きや多飲
-
頻尿
-
体重減少
-
倦怠感や疲れやすさ
-
手足のしびれや違和感
-
傷が治りにくい
-
目のかすみ
-
皮膚のかゆみ
特に、長期間血糖値が高い状態が続くと、合併症のリスクが高まるため、早めの受診が推奨されます。
糖尿病の合併症
糖尿病を放置すると、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。
1. 急性合併症
-
糖尿病性ケトアシドーシス:インスリン不足による高血糖が極端に進行し、意識障害を引き起こすことがあります。
-
高浸透圧高血糖症候群:極端な高血糖によって脱水症状が進み、命に関わる状態になることがあります。
2. 慢性合併症
-
細小血管障害(神経障害、網膜症、腎症):手足のしびれや感覚異常、視力低下、腎機能の低下などを引き起こします。
-
大血管障害(動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中):血管が狭くなり、心臓病や脳卒中のリスクが高まります。
-
歯周病:糖尿病患者は歯周病にかかりやすく、歯を失うリスクが高くなります。
糖尿病の予防と管理
糖尿病を予防し、進行を防ぐためには、以下のような生活習慣の改善が重要です。
1. 食事療法
-
バランスの取れた食事を心がける
-
糖質の過剰摂取を控える
-
野菜や食物繊維を多く摂る
-
塩分や脂肪の摂取を控える
-
ゆっくり食べる習慣をつける
-
間食を控え、規則正しい食事をする
2. 運動療法
-
ウォーキングや軽いジョギングを習慣にする
-
筋力トレーニングを取り入れる
-
1日30分程度の運動を継続する
-
階段を使うなど、日常生活に運動を取り入れる
3. 薬物療法
必要に応じて、医師の指導のもとで血糖値をコントロールする薬を使用します。インスリンの絶対的不足による1型糖尿病ではインスリン皮下注射が必須ですが、2型糖尿病の患者さんでは、内服薬やインスリン注射さらにはGLP-1作動薬の経口投与や皮下注射など数多くの選択肢があります。薬物療法のアルゴリズムとして日本糖尿病学会が策定した図を提示いたします。

当クリニックの基本姿勢は以下の通りです。
1) インスリンに依存するか否かの区別をつける 空腹時の血清Cペプチドの分泌状況で判断します
インスリン依存性と判明したときは当然のこととして上図のようにインスリンを使うことになります。
2) インスリン非依存性と判明した場合は大きく2つのアプローチがあります
治療目標であるHbA1cを患者さんと相談しながら個々に決めます。目安は以下。
| 血糖正常化 | 合併症予防 | 治療強化が困難 |
| HbA1c <6.0% | HbA1c <7.0% | HbA1c <8.0% |
3) 極力、インスリンは使わない方針でいきます
理由0 インスリンにも毒性・副作用があるからです(後日あらためて説明いたします)
理由1 医療経済的負担と連日のインスリン注射による煩雑さを回避して患者さんのQOLを挙げることに主眼を置きます
理由2 インスリン以外の内服薬や治療薬が大きく進歩して、それらの効果が十分期待できること
理由3 GLP-1受容体作動薬が大きな減量効果を有していることが判明し、肥満因子が強い方には初期から導入いたします
上の図でもBMI 25以上ではGLP-1がファーストラインに記載されています。
参考:この効果を利用して、当クリニックの減量外来を開設しました。
※他院でインスリン療法を導入されていても、希望されれば、少しずつ減量し他の薬物に切り替えていきます。最終的にはインスリンフリーを目指します。
4) 管理栄養士(週3日常駐)による適切な指導と看護師を含めたチーム医療を行います
5) 血管病変(大きな動脈と細小動脈)に対して適切に管理し、糖尿病の合併症を予防します
すなわち、大血管病である心筋梗塞・脳梗塞・下肢切断を防ぎ、細小血管病である血液透析導入・失明・神経症を防ぎます。
4. 定期的な検査
-
血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)の測定
-
血圧や中性脂肪・コレステロール値のチェック
-
尿検査と腎機能検査、尿ミネラル成分から食事摂取の把握
-
大血管病のチェックとして心電図・血管年齢のほか頸動脈エコーを1年ごとに検査します
-
細小血管病のチェックとして尿アルブミン測定、眼底検査およびアキレス腱反射などの神経系の検査を行います
-
フットケア(足の検査)も適宜行います
まとめ
糖尿病は適切な管理を行うことで、健康的な生活を送ることができます。食生活や運動習慣を見直し、定期的な検査を受けながら、合併症を予防することが大切です。少しでも気になる症状がある方や、糖尿病のリスクが気になる方、現在の治療に満足されていない方は、お気軽に当クリニックまでご相談ください。
2023/8/3 初稿
2025/4/25 第2稿