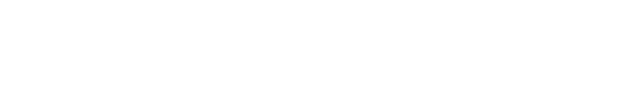骨粗しょう症について
骨粗しょう症について
〜骨の健康を守るために知っておきたいこと〜
1. はじめに
骨粗しょう症(こつそしょうしょう)は、骨の量(骨密度)や質が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。
特に女性の閉経後や高齢者に多く見られますが、男性にも起こります。
骨折は生活の質(QOL)を大きく下げ、寝たきりや認知症のリスクも高めるため、予防と早期発見がとても大切です。
骨粗しょう症は静かに進行するため、自覚症状が出にくく、「気づいたときには骨折していた」というケースも少なくありません。
2. 骨の働きと代謝の仕組み
骨は単なる体の支えではなく、全身の健康に関わる重要な臓器です。主な働きは以下のとおりです。
-
体を支える(支持作用)
-
内臓を守る(保護作用)
-
血液を作る(造血作用)
-
カルシウムやリンの貯蔵
-
ホルモン分泌(骨由来ホルモンによる代謝調節)
骨は一生同じ形を保つのではなく、「骨リモデリング」と呼ばれる作り替えを続けています。
-
骨芽細胞:新しい骨を作る細胞
-
破骨細胞:古い骨を壊す細胞
若い頃は骨形成が活発で骨量が増えますが、加齢やホルモン変化、栄養不足、運動不足などで骨吸収が優位になると骨量が減少します。
3. 骨粗しょう症の分類
原因により次のように分類されます。
(1) 原発性骨粗しょう症
他の病気が原因ではなく、加齢や閉経などが主因。
-
閉経後骨粗しょう症(女性に多い)
-
老年性骨粗しょう症(男女とも高齢期に発症)
(2) 続発性骨粗しょう症
特定の病気や薬の影響で起こる。
例:副甲状腺機能亢進症、甲状腺機能亢進症、糖尿病、慢性腎臓病、消化吸収不良症候群、ステロイド長期使用など。
4. 骨粗しょう症の症状
初期は無症状ですが、進行すると次のような変化が現れます。
-
背中や腰の慢性的な痛み
-
身長が縮む(圧迫骨折)
-
背中が丸くなる(円背)
-
転倒や軽い衝撃で骨折しやすい
骨折の部位は特に背骨(脊椎圧迫骨折)・手首・大腿骨頚部が多く、これらは生活に大きな支障を与えます。
5. 骨粗しょう症の危険因子
以下の条件が重なるほど発症リスクが高まります。
-
高齢(特に女性)
-
閉経
-
やせ型体型(BMI 18.5未満)
-
家族に骨粗しょう症や骨折の既往
-
運動不足
-
栄養不足(カルシウム・ビタミンD・タンパク質不足)
-
喫煙・多量飲酒
-
長期ステロイド使用
-
慢性疾患(糖尿病、腎疾患、肝疾患など)
6. 診断方法
(1) 骨密度測定(DXA法)
腰椎や大腿骨で測定し、若年成人平均値(YAM)70%未満なら骨粗しょう症と診断。
(2) 骨代謝マーカー
血液や尿で骨の作り替えの速度を確認。
(3) X線検査
背骨の圧迫骨折や形態変化を確認。
7. ビタミンD不足の重要性
当院のデータでは、日本人の約95%がビタミンD不足または欠乏。
主な原因は以下の通りです。
-
屋外活動不足(日光に当たらない生活)
-
食事からの摂取不足(魚離れ、干し椎茸などの摂取減少)
-
高齢による皮膚でのビタミンD生成低下
ビタミンDはカルシウム吸収を助け、骨形成を促進します。不足すると骨量減少や骨折リスクが高まります。
8. 生活習慣でできる予防
栄養
-
カルシウム:700〜800mg/日(牛乳、チーズ、小魚、青菜)
-
ビタミンD:400〜800IU/日(鮭、サンマ、干し椎茸、日光浴)
-
タンパク質:体重1kgあたり1.0〜1.2g(肉、魚、卵、大豆製品)
運動
-
ウォーキングや軽いジョギング
-
筋力トレーニング(スクワット、かかと上げ)
-
バランス訓練(片足立ち)
日光浴
-
1日15〜30分、腕や顔に日光を当てる
禁煙・節酒
-
喫煙は骨吸収を促進
-
過度の飲酒は骨代謝に悪影響
9. 薬物療法
症状や骨密度、骨折リスクに応じて薬を選びます。
-
骨吸収抑制薬:ビスホスホネート、デノスマブ、SERM
-
骨形成促進薬:テリパラチド、ロモソズマブ
-
ビタミンD製剤:アルファカルシドール、エルデカルシトール
10. 骨折予防の工夫
-
家の段差解消、滑り止めマット設置
-
明るい照明
-
手すりの活用
-
室内の整理整頓
11. 治療の流れ
-
骨密度測定
-
危険因子評価
-
栄養・運動指導
-
薬物療法導入
-
定期検査で経過確認
12. まとめ
骨粗しょう症は予防・早期治療で骨折を防げます。
当院では骨密度測定とビタミンD検査を行い、一人ひとりに合った治療を提案しています。
骨は年齢に関係なく鍛えられます。今日から骨の健康を意識しましょう。
別添イラスト(5点)
-
骨の構造と骨リモデリング
-
骨密度の年齢変化グラフ
-
ビタミンD生成経路図
-
骨折しやすい部位のイラスト
-
室内での転倒予防工夫図