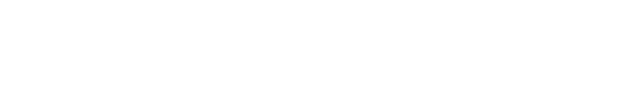亜鉛の働き
0.痩せすぎと亜鉛の関係
当院では2025/03/17から「瘦せすぎ外来」をオープンし、低体重に悩んでおられる方を対象に診療を始めました。同じタイミングで肥満に悩まれる方を対象に「減量外来」も始めました。痩せすぎ外来も意外と多くの方に検索していただき、実際外来においでいただいております。それも遠方からの患者様も多くみられます。「瘦せすぎ外来」に頻回に登場するキーワードであります亜鉛について基礎的知識を学びましょう。
1. 血清亜鉛濃度が低下するメカニズム
血清亜鉛は食事由来の供給が多いミネラルですが、意外と容易に低下することがあります。理由としては:
| 原因カテゴリー | 具体例 | メカニズム |
|---|---|---|
| 摂取不足 | 偏食(肉・魚・全粒穀物不足)、極端なダイエット、長期的な経腸・静脈栄養 | 食事中の亜鉛がそもそも少ない |
| 吸収障害 | 炎症性腸疾患、セリアック病、短腸症候群、慢性下痢 | 小腸上部での亜鉛吸収低下 |
| 吸収阻害因子の多い食事 | フィチン酸(玄米、大豆)、過剰カルシウム・鉄、ポリフェノール | 腸管内で亜鉛とキレート形成し吸収阻害 |
| 需要増加 | 成長期、妊娠・授乳、創傷治癒過程 | 体内利用量の増加 |
| 喪失増加 | 慢性下痢、多量発汗、腎疾患、火傷・滲出性皮膚病変 | 体外排泄が増える |
| 炎症・慢性疾患 | 感染症、慢性肝疾患、悪性腫瘍 | 亜鉛が肝臓に隔離され血中濃度が低下(急性期反応) |
2. 「そんなに簡単に下がるのか?」について
はい、短期間の摂取不足や吸収障害でも比較的容易に下がります。
血清亜鉛の基準値はおよそ 80–130 μg/dL ですが、60 μg/dL以下に低下する例は珍しくありません。
特に低体重患者さんでは以下が重なりやすく、低下しやすいです。
-
摂取量そのものが少ない
-
吸収面積の少ない腸内環境(胃切除後や慢性下痢)
-
低アルブミン血症による結合亜鉛の減少(亜鉛の大半はアルブミンに結合)
3. 食材に多く含まれる亜鉛と吸収率の落とし穴
亜鉛は牡蠣、牛肉、豚レバー、ナッツ類などに豊富ですが、「含有量が多い=必ずしも吸収される」とは限りません。
植物性食品はフィチン酸や食物繊維が多く、吸収率が低い傾向があります。
| 食材例 | 含有量(mg/100g) | 吸収率の目安 |
|---|---|---|
| 牡蠣(生) | 13.2 | 高(40〜50%) |
| 牛肩ロース | 6.8 | 高(30〜40%) |
| 玄米 | 2.1 | 低(10%以下) |
| 大豆 | 3.8 | 低(10%以下) |
4. 臨床的対応の目安
-
血清亜鉛 <60 μg/dL かつ症状あり(味覚障害、皮膚炎、脱毛など) → 補充検討
-
食事指導:高吸収性食品(動物性タンパク源)の摂取増加
-
サプリメント:硫酸亜鉛、酢酸亜鉛など(1日10〜30mg元素亜鉛として)
※長期高用量で銅欠乏に注意
5. リーキーガット症候群と亜鉛低下の関係
-
腸管バリア機能の破綻により、小腸粘膜上皮のタイトジャンクションが緩み、腸管内容物(細菌、毒素、未消化タンパク質など)が容易に血流へ移行する状態
-
慢性的な腸粘膜炎症、食物アレルギー様症状、全身性炎症の温床となる
(1) 吸収障害による低下
-
亜鉛は主に十二指腸〜空腸上部で吸収されます
-
リーキーガットでは粘膜の炎症・萎縮が起こり、
吸収上皮細胞(腸上皮細胞)数の減少と吸収能低下が生じます -
その結果、食事由来亜鉛の吸収効率が下がります
(2) 慢性炎症による分布変化
-
腸粘膜障害は全身性炎症反応を引き起こし、IL-6などのサイトカイン上昇
-
急性期反応として亜鉛は肝臓・網内系に取り込まれ、血中濃度が低下(実際には体内総量は変わらない場合もある)
(3) 腸管透過性亢進による喪失
-
リーキーガットはしばしば慢性下痢・脂肪便を伴い、
便中への亜鉛排泄増加が見られる -
特に脂肪便は脂肪酸と亜鉛がキレートを作り、吸収阻害+排泄増加の二重作用を生む
6. 低亜鉛状態がさらに腸を悪化させる悪循環
-
亜鉛はタイトジャンクションの構造維持と腸上皮細胞の再生に必須
-
低亜鉛状態ではバリア機能がさらに低下し、リーキーガットを悪化させる
-
このため、「リーキーガット → 低亜鉛血症 → 腸粘膜悪化 → さらにリーキーガット」という悪循環が成立しやすい
7. 臨床上の対応ポイント
-
モニタリング:血清亜鉛(Zn)+必要に応じてアルカリホスファターゼ(Zn依存酵素)測定
-
食事指導:吸収性の高い動物性タンパク質(牡蠣、赤身肉、レバーなど)
-
サプリメント:腸障害例では10〜30 mg/日(元素亜鉛量)を推奨、ただし銅欠乏予防のため長期高用量は注意
-
バリア修復:グルタミン、乳酸菌・ビフィズス菌、抗炎症性食事パターン(低FODMAPや精製糖質制限など)
2025/08/30 第1稿