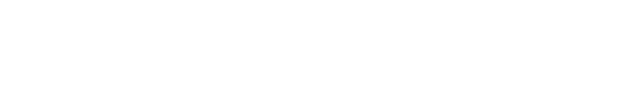シーボー(SIBO)って何ですか
シーボー(SIBO)とは何ですか?
小腸に細菌が増えすぎる状態
私たちの腸の中には、100兆個以上ともいわれる細菌がすんでいます。この「腸内細菌」は、大腸に集中していて、食べ物を分解したり、免疫を調整したり、ビタミンをつくったりと、健康に欠かせない働きをしています。
ところが、通常は少ないはずの小腸に細菌が増えすぎてしまうことがあります。この状態を SIBO(シーボー:小腸内細菌異常増殖症) と呼びます。Small Intestine Bacterial Overgrowthの略です。
なぜ小腸に細菌が増えてはいけないのか?
小腸は、本来「栄養を吸収する場所」であり、細菌が大腸ほど多く存在してはいません。そこに細菌が大量に入り込むと、食べ物の栄養を細菌に奪われてしまったり、ガスをつくられてお腹が張ったり、炎症を起こして下痢や痛みの原因になります。
シーボーの主な症状
SIBOがあると、以下のような症状が続くことがあります。
-
お腹の張り(ガスがたまる)
-
慢性的な下痢や便秘
-
食後の腹痛
-
栄養不足による体重減少
-
ビタミンB12欠乏、鉄欠乏などの栄養障害
-
倦怠感、集中力の低下
症状は「過敏性腸症候群(IBS)」に似ているため、長い間IBSと診断されていた方が、実はSIBOだったということもあります。
原因は?
SIBOの原因はひとつではありません。以下のような要因が重なって起こると考えられています。
-
腸の動きの低下
本来は小腸の内容物は下へ下へと送られていきますが、その動きが弱まると細菌が停滞して増殖します。 -
手術や癒着などによる腸の形の変化
盲ループ(食べ物がたまりやすい腸の袋状の部分)があると、細菌が増えやすくなります。 -
胃酸分泌の低下
胃酸は細菌を殺す働きがあります。胃酸が少ないと、細菌が小腸に入り込みやすくなります。逆流性食道炎のために胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)を飲んでいる方ではその可能性が高まります。 -
糖尿病や膠原病などの基礎疾患
神経や筋肉の動きが障害されることで、小腸の蠕動運動が弱くなり、SIBOのリスクが高まります。
診断方法
SIBOを診断するには「呼気テスト」がよく使われます。
ブドウ糖や乳果糖といった糖を飲んだ後に息を採取し、水素やメタンといったガスが増えるかどうかを調べます。小腸に細菌が多いと、糖を早い段階で分解してガスを出すため、呼気でそれが検出されます。
当院ではこの呼気テストは行っていませんが、実施しているクリニックさんもあり紹介することは可能です。ただし、自費診療になり数万円かかる可能性があります。
治療の考え方
治療は、原因を取り除くことと、症状を和らげることを目標に行います。
-
抗菌薬の内服:小腸内の細菌を減らすため、特定の抗菌薬(リファキシミンなど)が用いられることがあります。
-
食事療法:低FODMAP食(発酵性の糖質を控える食事)が有効なことがあります。
-
基礎疾患の治療:糖尿病や膠原病、手術後の癒着などの背景を整えることが重要です。
-
腸の動きを改善する薬:蠕動を助ける薬が使われることもあります。
SIBOと痩せすぎの関係
小腸に細菌が増えると、食べ物からの栄養吸収が妨げられ、体重が減ってしまうことがあります。特にビタミンB12や鉄の吸収不良が起こると、貧血や神経症状の原因になります。痩せすぎや栄養不良の背景に、SIBOが関わっている可能性があります。
まとめ
-
SIBO=小腸に細菌が増えすぎた状態
-
お腹の張り、下痢、便秘、体重減少などを引き起こす
-
呼気テストで診断できる
-
抗菌薬や食事療法で改善することがある
-
栄養不良や痩せすぎに関与することもある
「長年お腹の不調で悩んでいる」「いくら食べても体重が増えない」という方は、もしかするとSIBOが関係しているかもしれません。
※リーキーガット症候群との関係は?
これまでリーキーガット症候群と痩せすぎとの関連について話をしてきました。リーキーガット症候群では腸の上皮細胞同士の結合がゆるくなって、炎症をひきおこす物質や分子の体内への逆行を許して、体の不調を引き起こすと言って気ました。
今回のSIBOはそのメカニズムの中でどのような役割を果たすのか知りたくなると思います。「leaky gut症候群(腸管透過性亢進)」と「SIBO(小腸内細菌異常増殖)」は近接した概念であり、両者が低栄養・低体重と関係する場合もありますが、メカニズムや主因は少し異なるとされます。
🔹 Leaky Gut(リーキーガット症候群)
-
病態:小腸粘膜のバリア機能が破綻し、未消化物や毒素、細菌成分が血流に漏れやすくなる状態。
-
主な臨床像:慢性炎症、自己免疫疾患のリスク増大、アレルギー、倦怠感、腹部不快感など。
-
栄養状態への影響:
-
腸粘膜の炎症が続くと吸収不良を伴うことがある。
-
ただし「食べても太れない」という典型的な低体重に直結するよりは、慢性炎症・体調不良が主な特徴。
-
🔹 SIBO(Small Intestinal Bacterial Overgrowth:小腸内細菌異常増殖)
-
病態:通常は無菌に近い小腸に大腸由来の細菌が過剰に繁殖する状態。
-
主な症状:腹部膨満、下痢、ガス、栄養素吸収障害(特に脂溶性ビタミン、ビタミンB12、鉄)。
-
栄養状態への影響:
-
細菌が栄養素を先に利用 → 吸収不良。
-
脂肪や糖質の吸収障害 → 体重減少。
-
長期化すると「食べても太れない」や「低体重」に直結しやすい。
-
🔹 両者の関連
-
SIBOが存在すると、腸内炎症や粘膜障害を起こし、結果的に腸管透過性(leaky gut)が亢進することがある。
-
つまり SIBOがleaky gutを二次的に悪化させる ことはあるが、栄養障害に直結する主役はSIBOであるケースが多い。
✅ まとめ
-
Leaky gut:炎症や免疫異常と関係 → 全身不調は出るが、低体重の直接原因にはなりにくい。
-
SIBO:吸収不良を起こしやすく、「食べても太れない」という低体重により強く関連。
-
臨床的に「痩せすぎ・低体重」を訴える患者では、まず SIBOの関与を疑うのが妥当とされていますが、まだ議論の多い領域です。
- 学問の進歩とともに、さまざま考え方が提唱され、すこしずつ原因やメカニズムが明らかにされつつありますが、一方で複雑になりすぎる面もあり、よくわからなくなる心配もあります。当院では、お一人お一人の状態に合わせて身体所見や検査結果から解析してフィードバックしていきます。そして最適な治療方針を提案したいと思います。最終的にはご希望する体重および体型を手に入れましょう。
2025年9月24日 第1稿